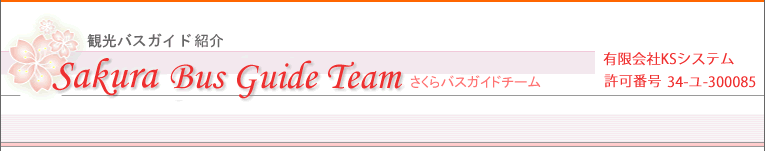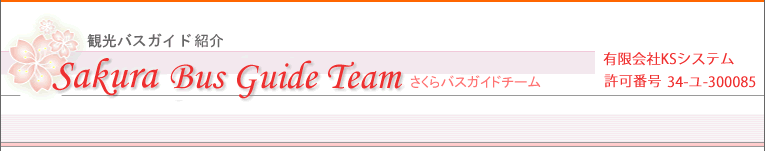|
苔寺(西芳寺) ― 静寂と緑が語る日本庭園
(2025.11.28)

皆さん、こんにちは。
やっと待ちわびた秋がやってきました。
が、少し寒くもなってきましたね、秋になるとどうしても京都に行きたくなる私ですが、
皆さんはいかがでしょうか?
以前、念願だったお寺に訪ねることができました。
そのお寺は、京都市西京区の山裾にひっそりと佇む西芳寺です。
通称「苔寺(こけでら)」 の名で広く知られるこのお寺は、その名の通り、
境内一面に広がる120種類以上の苔が織り成す「緑の絨毯」で世界的に有名ですね。
その深い緑の世界というのは、ただ美しいだけでなく、
日本庭園の歴史、禅の思想、自然と人の調和といった、日本文化の核心ではないかと思っています。
苔寺の歴史は古く、奈良時代の天平年間(西暦700年代)に前回、ご紹介した行基が開創したと伝えられます。
最初は法相宗の寺として建立されたのですが、荒廃と復興を繰り返し、
その後、室町時代に大きな転換期を迎えます。
この寺を再興したのが、庭園史に名を残す禅僧 夢窓疎石という方ですが、
彼は庭園作りの名手として名高く、京都の天龍寺・西芳寺・瑞泉寺など多くの寺院の庭を手掛けています。
その中でも西芳寺は、夢窓疎石の代表作で、「日本庭園の源流」とまで呼ばれる重要な存在となっています。
夢窓疎石が創り上げた西芳寺庭園は、上段に「枯山水庭園」、下段に「池泉回遊式庭園」を配した
二段構えの広大な庭園となっています。
現在見られる苔の庭は下段にあり、黄金池と呼ばれる心字形の池を中心に、
島や小さな橋などが配置されています。
しかし、苔寺が「苔の寺」として有名になったのは意外にも江戸期から明治にかけてのことだとされています。
室町時代の頃は、今のように苔は広がっていなかったようです。
ではなぜ苔が??
まず、お寺のある場所が、苔が育ちやすいこと、
高い湿度を保っていて、何より山裾の地形が苔にとっては理想的だったといわれています。
西芳寺は周囲を竹林と山に囲まれているのですが、風通しが良すぎず、
直射日光が少ない環境がベストだったのでしょう。
次に、あまり人の手が入らなかった時期が長く続いたことも功を奏しているようです。
手入れが行き届かない庭園というのは、苔にとってはむしろチャンスだったのかも。
現在、西芳寺で見られる苔の種類は 約120種類 といわれています。
同じ緑色といっても、微妙な質感や色の違いがありますが、代表的な苔として、
コツボゴケ、タマゴケ、ホソバオキナゴケ、ハイゴケなどがあります。
特に美しいといわれているのが、雨に濡れた苔で、「これこそが日本の美」と魅了されています。
苔寺はまた、世界的にも高く評価されているため、海外からの訪問者も多いのですが、
西芳寺では一般的な拝観は行われておらず、事前申し込み制の「写経参拝」 が基本となっています。
これは、庭園鑑賞が単なる観光ではなく、心を整え、自身と向き合う時間であってほしいという
思想が込められています。
写経が終わると庭園へ案内され、その世界へと足を踏み入れることができるのです。
庭園内を歩くと、島々を結ぶ小橋や、禅僧が修行をしたとされる「坐禅石」、
そして黄金池を囲む苔が、まるで絵巻物の中に入り込んだような光景を作り出していますが、
その苔には、気が遠くなるような大変な手入れ作業が必要で、
当然のことながら踏み込みは禁止されています。
苔寺の魅力は、ただ美しいというだけではなく、庭園に入った瞬間の静けさ、苔の匂い、
湿った空気が、訪れる人に時間を忘れさせてくれます。
私は観光バスの車内で、京都のお寺で知っている名前をおっしゃってみて下さい、
とお声がけすると、必ずといって良いほど、「苔寺」の名前が挙がります。
私たちバスガイドとしても、苔寺がコースに入っていることは非常に少ないのですが、
一度、個人的にもゆっくりと訪ねてみたいお寺の一つであることは間違いありません。
西芳寺(苔寺)
↓↓

|
| |
バックナンバーリスト 2025年11月
2025年10月
2025年09月
|
|