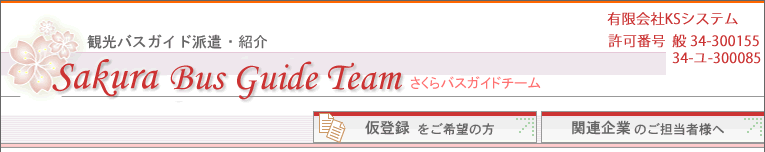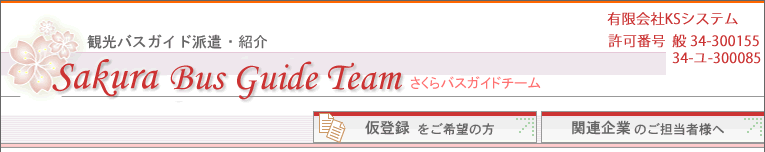|
| 鞍馬寺から貴船神社までのハイキングコース
|
皆さん、こんにちは!いよいよ待望の秋ですね。
最近は、観光バスツアーも一時期よりも数が少なくなっているようですが、
その分、少しマニアックなコースも多くなっているような気がするのですがいかがでしょうか、
例えば体験型のアクティビティを盛り込んだり、少し距離のある散策、ハイキングとまではいきませんが、
歩くことを取り入れたり、遊覧船、トロッコは以前からありましたが、ゆったりと観光するような内容の
コースが巷では人気のようです。
昔はツアーの数もとても多かったですし、間に合うのかハラハラしながらの盛りだくさんな内容で、
帰路の車内で、お客様と一緒に初日はどこどこへ訪ねましたね、など思い返してみるのですが、
たくさんありすぎて思い出せないことに笑いが起きていました。
珍しいコースといえば、次のお仕事が京都だというので、昼食は嵐山かな〜と想像しながら
確認してみると、鞍馬から貴船のハイキングがメインのコースで、
それは後にも先にもその一回だけでした。
鞍馬から多宝塔まではケーブル利用だったこともあり、お客様も気軽な感じで参加しておられて、
私が「歩く距離や時間的には短いけれど、平坦な道がないので・・」とご説明すると、
「この靴で大丈夫かしら?」とおっしゃった女性のお客様が、少し踵のある靴だったので、
私の下車案内用の靴を、サイズが合えば・・と貸して差し上げました。
私は個人的に2回ほど歩いたことがあるのですが、
ケーブルを降りてから先は、散策しながらゆったりと・・というようなことでは決してなく、
やはり「山」なので坂道も連続しますし、奥の院までの道は15分歩けばヘトヘトです。
何しろ、後の源義経となる牛若丸が修行したところだけあります。
もし、ケーブルを利用しなければ、大袈裟ではなく歩くための服装と心構えが必要です。
平安時代、清少納言が「近うて遠きもの くらまの九十九折といふ道」と枕草子に記しましたが、
清少納言は一体どういった服装でこの道を登ったんだろう?と想像しながら、
さすがに「ここは天狗が住んでいる山だもの」と思いながら歩いたことがあります。
※九十九折(つづらおり)
ところで、日本の有名な山々には天狗様がいらっしゃり、名前には「坊」がつきます。
ここで、日本の8大天狗を覚えておきましょう。
天狗にも小天狗・中天狗・大天狗とランクがありまして、中でも大天狗には
強力な神通力が備わっているとされます。
そもそも天狗は神様でもありますが、善悪の両方を持っているとのことで、妖怪とも称されます。
日本の8大天狗
-----------------
・愛宕山太郎坊(京都)あたごやまたろうぼう
・比良次郎坊(滋賀)ひらじろうぼう
・飯縄山三郎坊(長野)いいづなやまさぶろうぼう
・鞍馬山僧正坊(京都)くらまやまそうじょうぼう
・大仙伯耆坊(鳥取)だいせんほうきぼう
・英彦山豊前坊(福岡)ひこさんぶぜんぼう
・大峰山前鬼坊(奈良)おおみねさんぜんきぼう
・白峰相模坊(香川)しらみねさがみぼう
ちなみに牛若丸は、鞍馬山僧正坊に師事し、カラス天狗たちと鞍馬山で修行をしていたそうです。
鞍馬寺の歴史は古く、770年といいますので平安遷都の直前ですね。
759年に奈良の唐招提寺を創建した鑑真和上の高弟である鑑禎上人が白馬に導かれるようにして
鞍馬山に辿り着いたのですが、そこで鬼に襲われたところを毘沙門天に助けられたので、
毘沙門天を祀る鞍馬寺を創建しました。
毘沙門天といえば、北の方角を守護しますが、鞍馬寺には毘沙門天像が多く、
中でも筆頭は国宝の毘沙門天三尊立像です。
どっしりとした構えで右手に宝棒を持ち、左手は額にあてて、遠くを見守っている姿ですが、
高さは約170cmと大きく、栃の木の一木造りで本当に素晴らしいです。
特に、しかめっ面ではありますが、とても力強い表情でずっと見ていられます。
まずは写真で確認したい方は、
京都ミュージアム探訪様のサイトで「鞍馬寺」と検索なさってみて下さい。
鞍馬寺の霊宝殿が紹介されていますが、毘沙門天三尊立像の写真が添えられています。
また、機会があればぜひ、霊宝殿に実際に訪ねてみて下さいね。
さて、これからの季節、鞍馬から貴船までのコースは紅葉の見頃になるのでおすすめです。
車中でお客様にご説明すると、個人的に行ってみたい方々が、
距離とか所要時間について質問されることが多いので書いておきますが、
ケーブル利用で、降りてから鞍馬寺の金堂〜奥の院〜貴船神社まで、
普通の方の足で1.2時間くらい、距離にすると約1.5kmですが山道、坂道が続きます。
また、鞍馬寺の石段は155段、貴船神社の石段は87段です。
観光バスのコースでは、どうしても先に昼食でその後ハイキングコースとなるので、
食後の運動という形ですが、午前の早い時間帯からケーブル利用でコースを歩き、
貴船で昼食というのが私の個人的な理想です。
夏は川床料理が有名な貴船ですが、近年の夏は暑すぎるので、
やはり秋を選択してしまうかもしれませんが、精進料理などもありますので、
それも良いかなと考えています。
コース途中の見どころ:牛若丸が日々、修行をしたという木の根道
↓↓

このあたりは大昔、海底火山だったそうで、
岩盤がかたく、地中に根を伸ばせなかった結果、このようになったそうです。
貴船川沿いの紅葉も本当に美しく、足の疲れを癒してくれる景色ですね。
↓↓

(2024.10.29) |
|