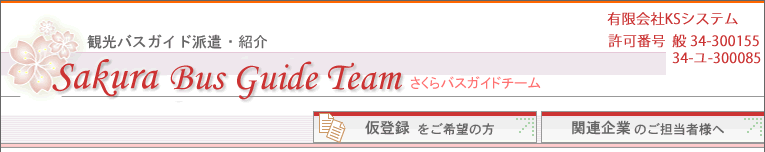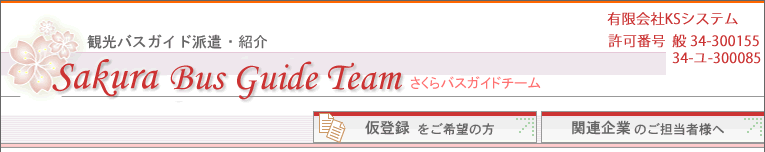|
| ガラス細工の美しさとその歴史
|
皆さん、こんにちは!今年もついに後半戦ですね。
急に寒くなって一気に冬に近づく実感も一入です。
ところで最近、友人から勾玉がついたアクセエサリーをプレゼントして頂きました。
勾玉といえば出雲あたりを思い出してしまうのですが、あの勾玉の形が何度見ても不思議で、
何となく古代ロマンを感じたり、パワーストーンのようなイメージがあります。
そのアクセサリーは、バッグにつけるような使い方なのですが、
「お守り」のように大事にしています。
勾玉は素材も様々なものがあるようですが、私が頂いた勾玉は「ストーン」です。
元々、勾玉とは縄文時代からの装具でガラス製、魔除けの意味合いも大きかったとのことです。
日本にガラスを作る技術が入ってきたのが弥生時代なので、たくさん作られるようになったのでしょう。
奈良時代の頃になれば、埋葬時に副葬品としても多く使われるようにもなります。
ガラスの起源はメソポタミアまで遡り、古代文明の頃からとは驚くばかりです。
その後は歴史を経て、アールヌーヴォー、アールデコといった芸術の域にまで発展し、
写真などを見ただけでも、その美しさには目を奪われてしまいます。
奈良の正倉院に、白瑠璃碗(はくるりわん)、瑠璃坏(るりのつき)という
ガラス製の椀とグラスがあるのですが、6世紀頃に作られたと考えられる、
ということが、どうしても信じられません!
その美しさは、どなたでも驚かれるのではないでしょうか?
つい先日まで、今年の「正倉院展」が開催されていましたが、
この白瑠璃碗、瑠璃坏はなかなか出典されていません。
平成20年の正倉院展で「白瑠璃碗」が久しぶりにお目見えしたのですが、
何と13年ぶりだったということなので、もしかしたら一生、本物は見ることができないかもしれません。
ちなみに「白瑠璃碗」はペルシャで作られたもので、シルクロードを超えて日本にやってきました。
ガラス工芸家の由水常雄氏が、白瑠璃碗と瑠璃坏を復元されていらっしゃるのですが、
それは本当に見事なもので、ずっと眺めていられるほどです。
由水常雄氏はガラス工芸技術のためヨーロッパに留学されており、
特別な思いを馳せて、復元に取り組まれたのだと思います。
由水常雄氏のサイトで、写真が掲載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい。
さて、白瑠璃碗、瑠璃坏は日本のものではないですが、
日本には、数々の名が知られたガラス細工があります。
私たちに馴染み深いところでは、鹿児島の薩摩切子、肥前びーどろは佐賀県ですね。
そして山口県の萩ガラス、特筆すべきは広島ガラスです。
広島には、世界に誇るTOHO(トーホー)があり、ガラスの里で吹きガラスを体験できたり、
親しまれていましたが、数年前に閉館してしまいましたので残念です。
萩ガラスは、素晴らしい特徴がたくさんあり過ぎて書ききれないのですが、
萩市の笠山からしか採取できない玄武岩を原料としていること、
私自身がどうしても手に入れたいと思っているのが、
わざとガラスに細かいヒビを入れてあるグラスで、何と耐熱です。
そしてまた、色が本当に美しいです。
「内貫入ガラス」で検索すると、たくさん出てきます。
その他、有名なガラス細工として、沖縄の琉球ガラス、皆さんもよくご存知の江戸切子、
大阪にも天満切子といって、まるで、万華鏡のように美しいガラス細工があります。
滋賀県の長浜というところに、「黒壁スクエア」というところがあり、
そこではガラス工芸品ショップの他、吹きガラスをはじめとする様々なガラス作り体験もできます。
元々、銀行だったのですが、何と広島ガラスを視察されて、
ガラス工芸をメインとした観光名所に生まれ変わったそうです。
また、ビードロは元々、織田信長の時代にオランダ・ポルトガルから製法が伝わりましたが、
今では独自の美しいガラス細工が続々と生まれていますね。
ビードロやギヤマンという呼称が、何となく異国情緒を感じるといいますか、
津軽びいどろや、肥前びーどろなど、ガラス工房を訪ねてみたくなりますね。
実は、私自身も一度ガラス細工に興味を持ち、「とんぼ玉」を自分で作ってみたことがあります。
ガラスが溶けると、まるで水飴のごとくドロドロになるのですが、
そこから丸い形に成形するのは本当に大変なこと!
温度が下がると当然ですが徐々にかたくなってくるのでスピードも重要です。
そんな大変さが身にしみてわかったところで、鑑賞専門となりました。
ガラス職人さんはすごいです!
内貫入と呼ばれるガラスの内側にヒビを入れてあります。
↓↓

(2024.11.29) |
|