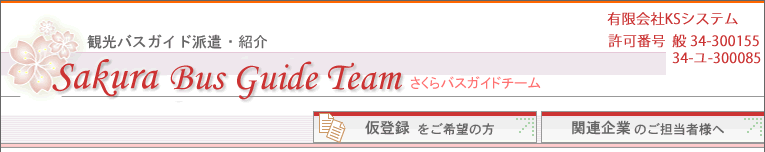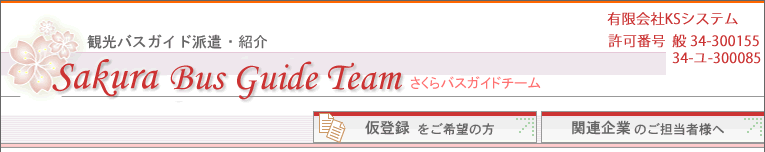|
| 大化の改新をざっくり説明します
|
皆さん、こんにちは。2024年もあと僅かとなりました。
今年は能登半島を中心とした地震をはじめとして、豪雨などの自然災害も多く、
約1年が経とうとしている今でも続く大変な現状に言葉もありません。
私自身、北陸には最も多いペースで行かせて頂いていましたので、
輪島の朝市は夏から少しずつ再開されているとニュースでみました。
ですが、もっともっと、たくさんの観光バスが朝市の駐車場に並ぶ日に向けて、
一日も早い復興と地元の皆様の安寧を心よりお祈り申し上げます。
さて、私がバスガイドとなった1年目、毎日のように京都・奈良コースを走り、
大阪・京都・奈良・神戸に関してはバスに乗車しての試験もありました。
広島出身の私が、まず最初に大変だったのは地理や歴史を覚えることでしたが、
知識も少しずつ増え、様々なコースに乗車する中で、
一番面白いなと感じたのが「飛鳥」でした。
石舞台古墳など、それまでお寺を中心とする観光地ばかりでしたから、
それが珍しいと思ったのかもしれません。
同期の友は、飛鳥は登場人物の名前が難しくて覚えにくいと言っていましたが、
確かにそうですね、私も最初は訳がわかりませんでした。
ですが、ガイドの指導員から「学校で習ったでしょ?」と言われた(覚えてない)
「大化改新」は、今思えば、最初に勉強しておくと良い気がします。
簡単にお話してみますと、
当時、蘇我稲目(そがのいなめ)という豪族がおり、天皇家に娘3人を
嫁がせたため、天皇家の外戚となり、権力を持ち始めます。
ガイド教本に出てくる蘇我馬子は稲目の子であり、聖徳太子は蘇我稲目のひ孫です。
つまり、聖徳太子と馬子は血縁関係にありますので、
2人は協力して政治を進めていくことになるのです。
このように、当時は天皇家と蘇我氏一族が絡み合っていたのですが、
どちらかというと蘇我氏との関係が薄く、皇室系の皇子として生まれるのが
中大兄皇子(なかのおおえのおおじ)です。
時を経て、蘇我入鹿(そがのいるか)が権力を持つようになり、
それは、天皇家をしのぐほどのものでした。
蘇我稲目 → 馬子 → 蝦夷 → 入鹿
さらに聖徳太子が亡くなると状況が悪化、蘇我入鹿が朝廷の政治を牛耳り、
それを憂いた天皇の子である中大兄皇子はどうしたものかと頭を悩ませていました。
そこで、中大兄皇子に仕えていた中臣鎌足(なかとみのかまたり)が
蘇我入鹿を討ってはどうか、と進言したと言われています。
ちなみに中臣鎌足は、中大兄皇子よりもひとまわりほど年上でした。
その後、飛鳥宮(板蓋宮/いたぶきのみや)で、蘇我入鹿は
中大兄皇子と中臣鎌足に暗殺されてしまうのです。
この事件が起こったのが645年6月です。
この事件により、蘇我氏の力が衰え、天皇家中心の政治に変わりました。
これを「大化の改新」と言います。
この時からずっと天皇家が政治の実権を握っていましたが、
鎌倉時代からは、幕府による政治が行われるようになります。
【参考】--------------------
鎌倉時代に再び、天皇家中心の政治を取り戻そうとした後鳥羽上皇は
「承久の乱」を起こしましたが失敗
さらに後醍醐天皇が「建武の新政」で実権を取り戻そうと、
2度の討幕を企てましたが失敗して隠岐へ流刑となってしまいました。
--------------------
お話を元に戻しますね、
大化の改新後、その功績を認められた中臣鎌足は、
朝廷から「藤原姓」を賜り、藤原鎌足となりました。
バスガイドとしての歴史学習は、範囲が広くて大変ですが、
NHKのEテレで放送されている「歴史にドキリ」という番組が
小学6年生向けではあるのですが、本当にわかりやすくてオススメです。
古墳時代から少しずつ時系列で勉強すると良いと思います。
また、飛鳥を巡るコースは観光バスの場合、
昼食と繋げて飛鳥資料館が入っていることが多く、
その後、石舞台古墳へ進むことが可能性大です。
さらに石舞台古墳からは、高松塚古墳ということもありますが、
私の場合、お里・沢一のお話をしつつ、壷阪寺へ行くことが多かったように思います。
壷阪寺の場合、時間があれば下車説明をすると喜ばれます。
藤原鎌足は、大原神社が生誕の地と言われ、産湯の井戸もあります。
飛鳥資料館から石舞台古墳に行く際には、大原神社が右側に見えます。
↓↓ 大原神社
飛鳥資料館を出ると、登り坂になるのですが、完全に登り切る手前に
名もなき信号があります。
万葉文化館のひとつ前の信号ですが、万葉文化館を過ぎると下り坂です。
その、名もなき信号を過ぎたところから右後ろを振り返るようにして見せます。
こんもりとした左の森は、藤原鎌足の母、大伴夫人の墓(円墳)、
その少し手前の塀が見えるところが鎌足生誕の地です。
(2024.12.28) |
|