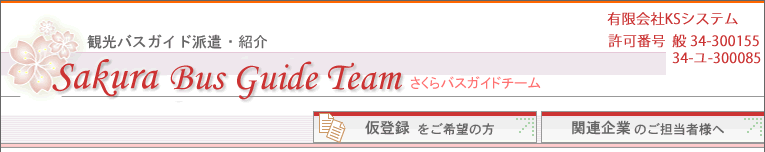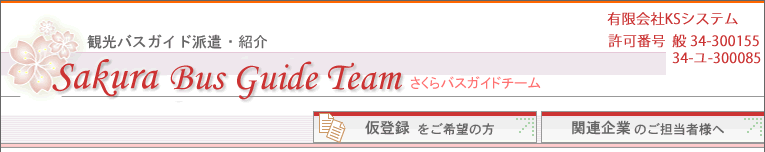|
| 興福寺の五重塔は修復中です。
|
皆さん、こんにちは。
春もたけなわ、徐々に暖かくなり、過ごしやすくなってまいりました。
興福寺は、669年に藤原鎌足の妻である鏡女王(かがみのおおきみ)が、鎌足の病気平癒を祈願するため、建立されたと伝えられます。
当初、興福寺とは呼ばれておらず、京都の山科にあったので山科寺(やましなでら)と言われていました。
その後、飛鳥 → 平城遷都とともに710年、平城京に移されて、「興福寺」となりました。
光明皇后の発願により、かの有名な五重塔が建てられたのは730年のことです。
時を経て平安時代、興福寺は隆盛を極め、170を超える堂塔が立ち並ぶほどの強大な勢力を誇ります。
しかしながら、これまで幾度の火災や戦乱により度々、焼失の憂き目に合ってしまいます。
特に、桃山時代には火災で多くの堂塔が消失し、さらに江戸時代には焼き討ちにも合いました。
現在の五重塔は、応永33年(1426)のものです。
※高さは50.937m
2023年7月より、五重塔は大規模な修理がおこなわれています。
この修理は、明治以来、実に120年ぶりとなる修理で、屋根瓦の葺き替え、漆喰の塗り直しなどが行われる予定です。
屋根を解体しての、かなり大がかりな修理で、完了は令和13年3月とのことです。
興福寺の五重塔といえば、猿沢池にその姿が映る美しい写真や、猿沢池の向こう側から緑の木々に囲まれた姿の写真がよくありますね。
それは、南都八景の一つに数えられるほどの絶景です。
昔から、猿沢池の七不思議として、
「澄まず、濁らず、出ず、入らず、蛙はわかず、藻は生えず、魚が七分に水三分」と伝えられ、
もし、水の色が変わったり、何か異変があった時には悪いことが起こる凶の前触れと言われました。
奈良時代、采女(うねめ)という女官がおりましたが、猿沢池に身を投げてしまい、
その後、池のほとりに祠が建てられました。
しかし、池を見るのが忍びなく、一夜のうちに池に背を向け、祠が反対側に向いてしまったそうです。
毎年、中秋の名月に行われる采女祭は、采女の霊を慰めるために始まりました。
采女神社で、中秋の名月の夜、月の明かりに照らしつつ、赤い糸を針に通すと願いが叶うと言われています。
近くに采女が衣をかけたと伝えられる衣かけ柳が残っています。
また、有名な旅籠「小刀屋善助」があったのも猿沢池のほとりです。
昔、猿沢池のほとりには印判屋庄右衛門、小刀屋善助、魚佐という大きな旅籠がありました。
小刀屋善助は一晩に4〜500人が宿泊したこともあるとのこと、
その時にわらじを一足も間違えなかったという逸話があります。
その小刀屋善助の観光案内も兼ねた、いわばパンフレットのようなものが残っており、
当時の様子が細かく伝わってきますので、ぜひ一度、ご覧下さい。
※御定宿小がたなや善助引札で検索
それは、大阪の松川半山という人が描いたもので、江戸時代後期から明治初頭にかけての様子がわかります。
当時としてはかなり豪華版のパンフレットであろうとのことです。
ところで、天理ICから奈良公園に向かう場合、左に旧大乗寺庭園を見ながら進むと、
池が見えてきますが、その池の向こうに現在修復中の興福寺五重塔が見えます。
但し、この池は猿沢池ではありません。
「荒池」というため池です。
奈良平野は雨が少なく、大きな川もないため、水不足になりやすいために作られました。
もともとは1589年、豊臣秀長が命じて作られたのが最初です。
まず、左に旧大乗寺庭園を見て進むと間もなく荒池がありますが、
下り坂になったらすぐに奈良ホテルの説明をして左上を見ると、1909年(明治42年)創業の奈良ホテルがあります。
その後は木々が邪魔して見えにくくなるのでタイミングを逃さないようにしましょう。
続いて、池の向こうの興福寺五重塔を見せます。
奈良ホテルは創業当時から建物が変わっていないということはもちろん、「まるごと明治時代」のような風格で
誰もが一度は泊まってみたいと思うであろうホテルです。
各国の大統領をはじめ、日本の皇族方も奈良に滞在される折にはこちらに宿泊されています。
ちなみに本館のロイヤルスイートは一泊約60万くらい、スタンダードで一泊約8万くらいです。
まず、左上の奈良ホテルを見て頂く
↓↓
続いて、池向こうの興福寺五重塔が見えます。
↓↓
ちなみに旧大乗寺庭園ですが、銀閣寺の庭を手がけた善阿弥(ぜんあみ)が京都から招かれて作庭したもので、
現在、国の名勝に指定されています。
善阿弥は、室町幕府8代将軍である足利義政に寵愛された作庭家です。
善阿弥の子は小四郎、孫は又四郎といいますが、いずれも作庭家で、小四郎は大乗寺庭園の作庭の際、善阿弥に同行しています。
また、銀閣寺においては、善阿弥、小四郎、又四郎と3代にわたって完成させたと伝えられます。
(2025.04.27) |
|