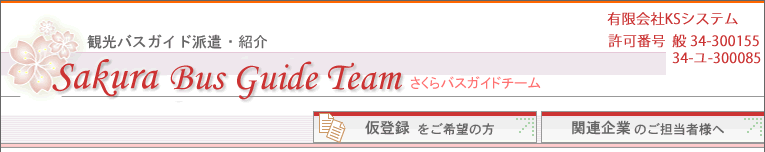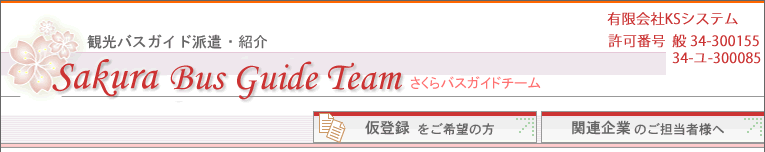|
| 京都〜 幻の西寺に想いを馳せる
|
皆さん、こんにちは。
新緑が目にまぶしく、観光にもぴったりの季節となりました。
関西万博もスタートしましたので、これから多くの観光客の皆様が各地へ訪れることになりますね。
私たちは、観光バスにて名神高速道路の京都南ICより市街地に入ることが多く、
最初に「東寺」の五重塔を車窓から見て頂くところより本格的な観光スタートとなりますが、
今回は、京都の南にかつて存在した「西寺(さいじ)」についてご紹介します。
何より観光地としては殆ど知られておらず、車中でご案内することも皆無かと思いますが、
実は、この「西寺」は、「東寺」と並び立つ国家の大寺院でした。
かつて、平安京が造営されたのは794年ですが、桓武天皇が長岡京から都を移した際、
都の入口となる羅城門の東西に二つの大寺が計画したのですが、それが「東寺(とうじ)」と「西寺(さいじ)」です。
この二つの寺は、当時の国家によって造られた「官寺(かんじ)」であり、左右対称に配置されていました。
現在でも大伽藍を残す東寺は広く知られていますが、かつて西寺もそれと同じ規模の堂塔を備えた大寺院でした。
その後、823年に嵯峨天皇は、東寺を弘法大師・空海に下賜し、その管理を任せます。
その一方で、西寺の管理を命じられたのが「守敏(しゅびん)」という僧侶でした。
この二人は仏教界でも思想的に対立していたと伝えられ、有名な「雨乞い対決」の逸話があります。
ある年、都は長い間日照りに見舞われ、深刻な事態となっていました。
そこで朝廷は、空海と守敏に雨を乞う祈祷をするよう命じたのです。
空海は、東寺で真言密教による祈祷を行い、何と雨を降らせることに成功、
しかし、これに対抗する守敏は、雷だけが鳴って雨は降らなかったそうです。
この一件により、空海の霊験が広く知られることとなり、
以後、東寺は真言宗の総本山として発展していくことになります。
一方の守敏と西寺は、しだいに人々の記憶から遠ざかっていきました。
さらに西寺は、度重なる火災や戦乱の影響で衰退していくのですが、
特に平安後期には荒廃が進み、鎌倉時代以降は伽藍も失われ、ついには完全に姿を消してしまいます。
現在、かつての西寺の跡地は、京都市南区唐橋(からはし)にある「西寺公園」として整備されています。
公園の片隅には「西寺跡」と記された石碑が残るのみですが、
2019年、その近くで12カ所の穴跡が見つかってニュースにもなりました。
当時、東寺と西寺は朱雀大路を挟んで左右対称だったとされることから、
西寺の五重塔跡の可能性が非常に高いといわれています。
そして何と!その後の調査で、柱の間隔が東寺の五重塔と殆ど同じだとか、
これは、今後の調査に期待がかかりますね。
特に、東寺と西寺は官営の寺院として同じ時期に造営されていますが、
当時は西寺の方が格が上であったという説は有力です。
地図を開くと、羅城門跡をはさんで東側に東寺、西側に西寺跡が位置していたことが分かりますので、
皆さんも一度、確認なさってみて下さいね。
この配置については、都の守りの要として、いかにこの二つの寺が重要だったかを示しています。
東寺の五重塔を見て頂いた後、通常ルートでは堀川通りに入ることが多く、
次のポイントは西本願寺になりますが、もし手前の交差点で信号待ちになった場合、
「実はこのお寺には対になる“西寺”がありました」とお話しても良いですね。
さらに時間があれば、簡単にでも空海と守敏の雨乞い対決の伝説を入れることで、
歴史の奥行きを感じさせることができます。
〜 姿は消えても、歴史は残る 〜
西寺は今では完全に失われた「幻の大寺院」ですが、東寺と並び称された国家的寺院であったという
事実は、平安京の構造や仏教の展開を知る上で欠かせない要素です。
西寺跡
↓↓

(2025.05.28) |
|