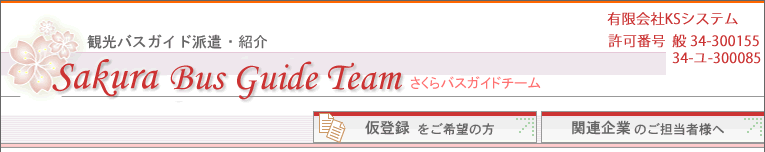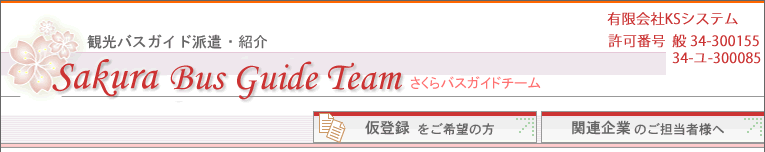|
| 嵯峨天皇ゆかりの御所
|
皆さん、こんにちは。
青もみじが目に鮮やかに映る季節となりました、今年は雨が多いとのことで梅雨は憂鬱ではありますが、
紫陽花やハナショウブ、スイレンなどを筆頭に美しいお花が見られる頃なので、楽しみたいですね。
さて前回、嵯峨天皇が823年、東寺を弘法大師・空海に下賜したというお話をさせて頂きましたが、
その嵯峨天皇ゆかりのお寺、名刹「大覚寺(だいかくじ)」についてです。
通常は金閣寺を観光すると、そこから嵯峨野へ向かうコースが定番ルートとなりますが、
途中、広沢の池を右手に見てほどなく大覚寺門前の交差点にさしかかりますが、
そこから右折したところに大覚寺があります。
大覚寺の起源は、平安時代初期にさかのぼります。
もともとは第52代・嵯峨天皇の離宮「嵯峨院(さがいん)」として建立されましたが、
天皇が崩御したのち、876年にその御所を寺院に改めたのが始まりです。
つまり、大覚寺はもともと天皇の御所だったということですね。
また、大覚寺は、いけばなの嵯峨御流の発祥地であることも忘れてはなりません。
これは、嵯峨天皇が大沢池の水面に浮かぶ花を愛でたことが始まりとされるのですが、
現在も、大覚寺は嵯峨御流の家元となっておりますので、全国から花道家が訪れています。
ところで、大覚寺は皇族の男子が出家して住職を務める「門跡寺院(もんぜきじいん)」のひとつです。
特に、室町時代には天皇の皇子が入寺したこともあり、「嵯峨御所」とも呼ばれていました。
例えば、室町幕府第3代将軍・足利義満の子、義昭も住職を務めました。
そのため、建物や庭園には御所のような、格式高い雰囲気を今に伝えています。
さて、大覚寺の境内の東側は大沢池です。
時代劇のロケ地として有名で、多くの俳優さんが大沢池に入って演技されました。
↓↓

大沢池(おおさわのいけ)は、かつて平安貴族たちが舟を浮かべ、詩を詠み、月を眺めました。
周囲約1kmのこの池は、嵯峨天皇が中国・唐の洞庭湖(どうていこ)を模して造らせたといわれます。
中秋の名月の日には、池に舟を浮かべて月を愛でる「観月の宴」が開かれます。
また、ロケといえば大覚寺の表門の横に「明智門」という白い門があるのですが、
例えば、必殺シリーズでは南町奉行所として使われたロケ地で、皆さんも見たことがおありと思います。
明智光秀が居城した亀山城から移築されたと伝えられ、「明智門」と呼ばれています。
ここで、嵯峨天皇について追記しておきたいと思いますが、
嵯峨天皇は、第52代天皇であり、在位は809年〜823年です。
父は桓武天皇です。
嵯峨天皇のが治めた時代は、平安時代初期の頃の安定期にあたります。
前回のお話にありましたように、東寺・西寺はこのときの国家プロジェクトで、
嵯峨天皇の意向で創建されました。
その後の823年、嵯峨天皇は東寺を空海に、西寺を守敏に下賜しました。
これ以降、真言宗が隆盛する大きなきっかけとなったのです。
この空海や最澄、橘逸勢などもこの時期の人物ですが、
嵯峨天皇は、三筆(さんぴつ)の一人としても知られ、空海や橘逸勢と並ぶ名筆家でした。
もし、タイムマシンなるものがあったなら、
この時代に行って、空海に会ってみたいと切に思いました。
大覚寺門前
↓↓
(2025.06.28) |
|